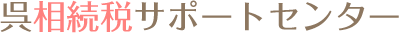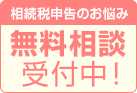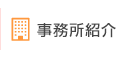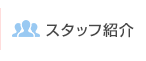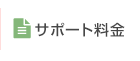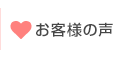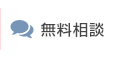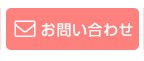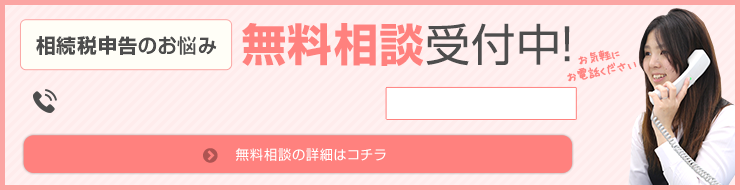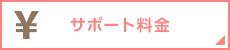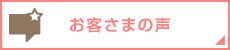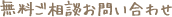【税理士が解説】相続税の配偶者控除のポイントとは?
「配偶者が亡くなった後の相続、多額の相続税がかかるのでは…」と不安に思われる方は少なくありません。
しかし、日本の相続税法には、残された配偶者の生活保障などを目的とした手厚い軽減制度が設けられています。
それが「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)」です。
この制度を正しく理解し、活用することで、多くの場合、配偶者の相続税負担をゼロに、あるいは大幅に軽減することが可能です。本コラムでは、相続税の配偶者控除の基本的な仕組みから、最大限に活用するためのポイント、注意点まで、税理士が分かりやすく解説します。
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産を相続する場合に利用できる、非常に強力な相続税の軽減措置です。
具体的には、配偶者が相続した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。
この制度の背景には、残された配偶者の今後の生活を保障するという目的や、夫婦で協力して築き上げた財産に対する貢献を考慮するという考え方があります。
相続税における配偶者控除の基本ルール
配偶者控除の計算の基礎となるのは、前述の通り「1億6,000万円」と「法定相続分」です。
• 1億6,000万円: これは無条件で控除が認められる金額の基準です。配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、法定相続分がいくらであっても相続税はかかりません。
• 法定相続分: 民法で定められた相続割合のことです。遺産の総額が1億6,000万円を超える場合でも、配偶者が法定相続分までの財産を相続するのであれば、相続税は課されません。
法定相続分は、他に誰が相続人になるかによって変動します。例えば、他に相続人が子のみの場合は配偶者の法定相続分は1/2、親(直系尊属)のみの場合は2/3、兄弟姉妹のみの場合は3/4となります。相続人が配偶者のみであれば、配偶者がすべての遺産を相続します。
例えば、遺産総額が3億円で、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の法定相続分は1億5,000万円(3億円 × 1/2)です。この場合、「1億6,000万円」の方が多いので、配偶者は最大1億6,000万円まで相続しても相続税はかかりません。
もし遺産総額が4億円であれば、配偶者の法定相続分は2億円(4億円 × 1/2)となります。この場合は「法定相続分」の方が多いため、配偶者は最大2億円まで相続しても相続税はかかりません。
配偶者控除を利用するための条件と手続き
この有利な制度を利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
1. 戸籍上の配偶者であること: 法律上の婚姻関係にあることが絶対条件です。長年連れ添った内縁関係(事実婚)のパートナーは、残念ながらこの控除の対象外となります。
2. 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること: 誰がどの財産をいくら相続するかが、相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに確定している必要があります。遺産分割協議がまとまらない場合、原則としてこの控除は適用できません。
3. 相続税の申告書を税務署に提出すること: 配偶者控除を適用した結果、相続税額が0円になる場合でも、必ず相続税の申告手続きが必要です。申告をしなければ、控除の適用を受けることはできません。
手続きに必要な主な書類
• 相続税の申告書
• 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
• 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
• 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
配偶者控除を最大限に利用するためのポイント
配偶者控除は非常に強力ですが、無計画に利用すると将来的に損をしてしまう可能性があります。重要なのは、「二次相続」まで見据えた対策です。
二次相続とは? 一次相続は、今回亡くなった方(例:夫)からの相続です。二次相続とは、その次に、残された配偶者(例:妻)が亡くなった際の相続を指します。
一次相続で配偶者控除を最大限に利用し、配偶者が多くの財産を相続したとします。その結果、一次相続の相続税は大幅に抑えられるかもしれません。しかし、その配偶者が亡くなった時(二次相続)には、その多くの財産が子どもたちに相続されます。二次相続では、当然ながら配偶者控除は使えません。また、相続人が減ることで基礎控除額も少なくなり、結果として一次・二次を合わせたトータルの相続税額が高額になってしまうケースがあるのです。
ポイント
• 二次相続をシミュレーションする: 一次相続の際に、二次相続でどれくらいの税負担が発生するかを試算し、一次相続で配偶者がどれくらいの財産を相続するのが最適かを検討します。
• 配偶者の生活資金を確保する: 税金のことだけを考えるのではなく、残された配偶者が安心して生活するために必要な資金を最優先に考えましょう。
• 子どもへの相続も検討する: 一次相続の段階から、一部の財産を子どもに直接相続させることも有効な選択肢です。
配偶者控除と小規模宅地等の特例の併用について
自宅や事業用の土地を相続する場合には、「小規模宅地等の特例」という制度があり、土地の評価額を最大80%減額できます。この特例と配偶者控除は併用が可能です。
併用することで、極めて大きな節税効果が期待できます。例えば、評価額の高い自宅の土地を配偶者が相続する場合、まず小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を大幅に圧縮します。その上で、他の預金などの財産と合わせた相続額に対して配偶者控除を適用するのです。
たとえ配偶者控除だけで相続税がゼロになるケースであっても、小規模宅地等の特例を併用すべき場合があります。特例を適用することで、課税対象となる遺産の総額自体が圧縮されるため、配偶者以外の相続人(子どもなど)の相続税負担を軽減できる可能性があるからです。
配偶者控除を受けられないケースとは
以下のようなケースでは、配偶者控除の適用が受けられませんので注意が必要です。
• 内縁関係の配偶者: 法律上の婚姻届を提出していない場合は対象外です。
• 相続税の申告をしなかった: 控除適用で税額がゼロになるとしても、申告は必須です。無申告の場合は適用を受けられません。
• 申告期限までに遺産分割が未了: 原則として適用できません。ただし、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、実際に3年以内に分割が完了すれば、後から控除を適用(更正の請求)することが可能です。
• 財産を隠していた場合(仮装・隠蔽): 意図的に財産を隠して申告した場合、その隠した財産については配偶者控除の対象となりません。
まとめ
相続税の配偶者控除は、残された配偶者の生活を守るための非常に重要な制度です。1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからないという大きなメリットがありますが、その恩恵を最大限に、かつ賢く受けるためには、制度の正しい理解が不可欠です。
特に、二次相続まで含めた長期的な視点でのプランニングや、小規模宅地等の特例との併用は、専門的な知識が求められる部分です。相続が発生した際、または将来の相続に備える際には、一度相続に詳しい税理士に相談し、ご自身の家族にとって最も有利な分割方法や申告方法を検討することをお勧めします。